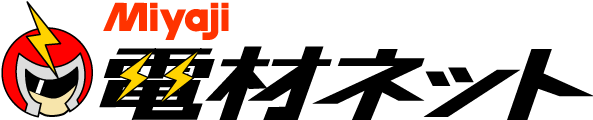「家の電球が切れたから、これを機に省エネで長持ちするLED電球に交換したい」 「でも、お店に行ったら種類が多すぎて、どれを選べばいいかさっぱり分からない…」
そんなお悩みはありませんか? LED電球は、電気代を節約できて寿命も長い、とても優れた照明です。しかし、口金(くちがね)のサイズや明るさ、光の色など、選ぶときに確認すべきポイントが多く、初心者には少し難しく感じるかもしれません。
せっかく買ったのに「サイズが合わなかった」「思ったより暗かった」といった失敗は避けたいですよね。
この記事では、LED電球の専門家として、誰でも迷わず自宅にぴったりの製品を選べるように、選び方の手順を分かりやすく徹底解説します。この記事を最後まで読めば、あなたもLED電球選びの達人になれるはずです。
目次
【手順1】口金サイズの種類と確認方法
LED電球選びで、**まず最初に確認すべき最も重要なポイントが「口金(くちがね)のサイズ」**です。口金とは、電球の根元にある金属のねじ込み部分のことで、照明器具のソケットに合わないと取り付けることができません。
主要な口金はE26とE17の2種類
日本の家庭で使われている照明器具の口金は、主に以下の2種類です。
- E26(イーにじゅうろく) 直径が26mmの、最も一般的なサイズの口金です。リビングのシーリングライトやダイニングのペンダントライト、スタンドライトなど、家の中のさまざまな場所で広く使われています。
- E17(イーじゅうなな) 直径が17mmの、E26より一回り小さいサイズの口金です。ダウンライトやシャンデリア、スポットライト、玄関灯など、小型の照明器具でよく使用されます。
まずはご自宅の照明器具の口金がどちらのサイズかを確認しましょう。
使用中の電球の口金サイズを測る方法
口金サイズの確認方法はとても簡単です。
一番確実なのは、今ついている電球を外して、口金の近くに印字されている型番を見ることです。「E26」や「E17」といった表記が必ずどこかに書かれています。
もし印字が消えていて読めない場合は、定規で口金の直径を測ってみましょう。金属部分の直径が約26mmならE26、約17mmならE17です。火傷や感電の危険を避けるため、必ず照明のスイッチを切り、電球が冷めてから作業してください。
ピンタイプなど特殊な口金の種類
ごくまれに、E26やE17以外の特殊な口金が使われていることがあります。
- E11 / E12 E17よりもさらに小さいサイズのねじ込み式口金です。装飾照明や常夜灯などに使われます。
- G4 / GU5.3 / GU10など(ピンタイプ) 2本のピンを差し込むタイプの口金です。ハロゲンランプの代替として、スポットライトなどで使用されます。
もしご自宅の電球がこれらの特殊な形状だった場合は、外した電球の型番を正確にメモし、同じ型番のLED電球を探すのが最も確実な方法です。
【手順2】明るさの選び方|ワットとルーメンの目安
口金のサイズが分かったら、次に「明るさ」を選びます。ここで多くの人がつまずきがちですが、ポイントさえ押さえれば簡単です。
明るさの単位はルーメン(lm)で見る
LED電球の明るさを選ぶ際は、「ルーメン(lm)」という単位に注目してください。
- ルーメン(lm)とは 光源が放つ光の総量、つまり「本当の明るさ」を示す単位です。この数値が大きいほど、電球は明るくなります。
- ワット(W)とは 消費電力を示す単位です。白熱電球の時代は「60Wの電球」のようにワット数が明るさの目安でしたが、LED電球は非常に少ない消費電力(ワット数)で明るく光ります。
そのため、異なるメーカーのLED電球の明るさを比較するときは、ワット数ではなくルーメンの数値で比較するのが正解です。
白熱電球との明るさ(W相当)比較表
今まで白熱電球を使っていた方のために、多くのLED電球のパッケージには「60W形相当」のように、従来の電球に換算した場合の明るさが記載されています。
以下が、白熱電球のワット数とLED電球のルーメンの目安です。
| 白熱電球の明るさ | LED電球で必要な明るさ(目安) |
|---|---|
| 20W形 相当 | 230 lm 以上 |
| 40W形 相当 | 485 lm 以上 |
| 60W形 相当 | 810 lm 以上 |
| 100W形 相当 | 1520 lm 以上 |
(参考:一般社団法人 日本照明工業会 ガイドA 121-2022)
例えば、今まで60Wの白熱電球を使っていた場所には、810lm以上のLED電球を選べば、ほぼ同じ明るさが得られます。
部屋の広さと用途別のおすすめの明るさ
部屋の広さや使い方によって、最適な明るさは変わります。以下に目安をまとめました。
- リビング(〜8畳程度) 部屋全体を明るくしたい場合は、100W相当(1520lm)以上のものを主照明に。複数の照明を使うなら**60W相当(810lm)**を組み合わせるのがおすすめです。
- ダイニング 食卓を美味しく照らすには**40W〜60W相当(485〜810lm)**が人気です。
- 寝室 リラックスできる空間にするため、少し暗めの**40W〜60W相当(485〜810lm)**が良いでしょう。
- 書斎・勉強部屋 文字を読んだり作業したりする場所なので、手元がしっかり見える60W相当(810lm)以上が適しています。
- トイレ・廊下・玄関 **40W相当(485lm)**程度の明るさがあれば十分です。
【手順3】光の色の選び方|3種類の光色と特徴
明るさが決まったら、次は光の色(光色)を選びましょう。光色によって部屋の雰囲気は大きく変わります。主な光色は「電球色」「昼白色」「昼光色」の3種類です。
電球色・昼白色・昼光色の違いと比較
それぞれの光色の特徴と、与える印象を比較してみましょう。
- 電球色(でんきゅうしょく) 夕日のような暖かみのあるオレンジ色の光です。リラックス効果が高く、料理を美味しそうに見せる効果もあります。
- 昼白色(ちゅうはくしょく) 太陽の光に近い、自然で生き生きとした白色の光です。どんな部屋にも合わせやすく、最も標準的な色と言えます。
- 昼光色(ちゅうこうしょく) 青みがかった、最も明るく涼しげな印象の白色の光です。脳を覚醒させ、集中力を高める効果があるため、細かい作業に向いています。
リビングや寝室など場所別のおすすめ光色
光色の特徴を活かして、お部屋の用途に合った色を選びましょう。
- リビング 家族団らんの時間は「電球色」、日中のように活動的に過ごしたいなら「昼白色」がおすすめです。
- ダイニング 料理が引き立つ「電球色」が最適です。
- 寝室 心と体を休める場所なので、リラックスできる「電球色」一択です。
- 書斎・勉強部屋 集中して作業したいなら「昼光色」、長時間の作業で目が疲れにくいのは「昼白色」です。
- キッチン・洗面所 食材の色やメイクの色味を正確に確認できる「昼白色」が向いています。
【手順4】形状と光の広がり方(配光)の選び方
最後のステップは、電球の「形状」と「光の広がり方(配光)」です。照明器具のデザインや、光をどのように届けたいかによって最適なものが異なります。
一般電球形・ボール形など形状の種類
LED電球には、白熱電球と同じように様々な形があります。
- 一般電球形(A形) 最もポピュラーなナスのような形です。どんな器具にも合わせやすい万能タイプです。
- ボール形(G形) 丸いボールのような形状です。存在感があり、電球そのものを見せるようなデザインの照明器具によく合います。
- T形 細長い筒状の形をしています。ソケットが横や斜め向きについているダウンライトなど、狭いスペースにも収まりやすいのが特徴です。
- シャンデリア形(C形) ろうそくの炎のような形をした装飾性の高い電球です。シャンデリアに最適です。
全方向・広配光・下方向タイプの違い
形状と合わせて、光がどのくらいの角度に広がるか(配光)もチェックしましょう。
- 全方向タイプ(約260°〜300°以上) 白熱電球とほぼ同じように、空間全体を明るく照らします。リビングの主照明など、部屋全体を明るくしたい場合におすすめです。
- 広配光タイプ(約180°) 電球の半分より広い範囲を照らします。ダイニングやリビングなど、広い範囲をカバーしたい場合に適しています。
- 下方向タイプ(約120°) 光が下方向に集中するため、一方向をピンポイントで明るくしたい場合に最適です。ダウンライトやスポットライトに向いています。
照明器具にシェードやカバーがあるか、どこを照らしたいかを考えて選ぶと、より快適な空間を作ることができます。
交換時の注意点|LED電球が使えない照明器具
LED電球は万能に見えますが、一部の特殊な照明器具では使用できなかったり、専用の「対応品」を選ぶ必要があったりします。購入前に必ずご自宅の照明器具を確認してください。
調光機能付き照明器具
調光機能とは、壁のスイッチやリモコンで明るさを自由に調節できる機能のことです。 この機能が付いた照明器具に、「調光器対応」と書かれていない普通のLED電球を使用すると、ちらつきや不点灯、最悪の場合は電球や器具の故障につながります。 必ずパッケージに「調光器対応」の記載がある製品を選んでください。
密閉型照明器具(浴室・玄関灯)
密閉型器具とは、浴室の照明や玄関灯のように、ガラスやプラスチックのカバーで電球が完全に覆われている器具を指します。 LEDは熱に弱いため、熱がこもりやすい密閉型器具で非対応の製品を使うと、著しく寿命が短くなる原因となります。 このような場所には、必ず「密閉型器具対応」と表示されたLED電球を使用しましょう。
断熱材施工器具(ダウンライト)
断熱材施工器具とは、天井に埋め込まれたダウンライトの周りを、建物の断熱材が覆っているタイプの器具です。これも熱がこもりやすいため、専用の対応品が必要です。 照明器具に**「SB」「SGI」「SG」のいずれかのマーク**が付いている場合は、必ず「断熱材施工器具対応」のLED電球を選んでください。
LED電球の性能比較とよくある質問
最後に、LED電球の優れた性能と、交換時によくある疑問についてお答えします。
白熱電球・蛍光灯との電気代・寿命比較
LED電球は、白熱電球や電球型蛍光灯と比べてどのくらいお得なのでしょうか。性能を比較してみましょう。
| 項目 | LED電球 | 電球型蛍光灯 | 白熱電球 |
|---|---|---|---|
| 消費電力(60W相当) | 約7W | 約12W | 54W |
| 定格寿命 | 約40,000時間 | 約6,000時間 | 約1,000時間 |
| 1年間の電気代(※) | 約643円 | 約1,104円 | 約4,967円 |
※1日8時間、365日使用、電気料金単価31円/kWhで計算した場合の目安
表の通り、LED電球は圧倒的に長寿命で、消費電力も少ないことが分かります。初期費用は他の電球より少し高いですが、交換の手間や電気代を考えると、長い目で見て最も経済的です。
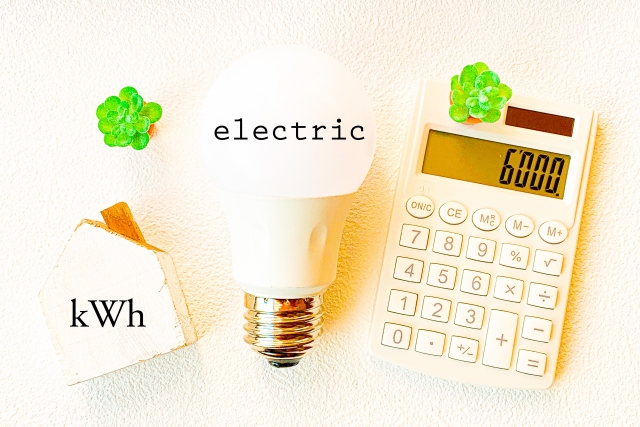
Q. 浴室におすすめのLED電球は?
A. 「密閉型器具対応」のもので、光色は「昼白色」がおすすめです。
浴室の照明は湿気対策のためカバーで覆われていることがほとんどなので、熱に強い**「密閉型器具対応」は必須**です。また、体のコンディションをチェックしたり、掃除をしたりする際には、モノの色が自然に見える「昼白色」が適しています。
まとめ
今回は、失敗しないLED電球の選び方について、4つのステップと注意点を解説しました。最後に、重要なポイントをもう一度おさらいしましょう。
- 手順1:口金サイズを確認する まずは自宅の照明器具の口金が「E26」か「E17」かを確認しましょう。
- 手順2:明るさ(ルーメン)を選ぶ 明るさは「W(ワット)相当」を参考にしつつ、「lm(ルーメン)」の数値で比較します。
- 手順3:光の色を選ぶ リラックスしたいなら「電球色」、自然な光なら「昼白色」、集中したいなら「昼光色」と、用途に合わせて選びましょう。
- 手順4:形状と光の広がり方を選ぶ 照明器具のデザインや、どこを照らしたいかに合わせて、形状と配光(全方向・広配光・下方向)を選びます。
そして、交換時には**「調光器」「密閉型器具」「断熱材施工器具」**に該当しないか、必ず確認してください。
この記事を参考に、ぜひあなたの家にぴったりのLED電球を見つけて、快適で経済的なあかりのある生活をスタートさせてください。