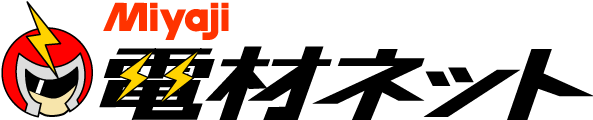「この建物に非常灯(非常用照明装置)は必要なのか?」「設置するなら、どんな基準を守ればいいのだろう?」 建物の設計や管理に携わる中で、このような疑問をお持ちではないでしょうか。
非常用照明の設置基準は、人々の安全を確保するための重要な法規制です。しかし、その内容は建築基準法や消防法にまたがり、複雑で分かりにくい部分も少なくありません。
この記事では、建築士や施工管理者、建物の管理担当者の方に向けて、非常用照明の設置基準を徹底的に解説します。根拠となる法律の違いから、具体的な設置義務、技術基準、緩和条件まで、専門的な内容を分かりやすく整理しました。
この記事を読めば、非常用照明に関する法規制を正確に理解し、設計・施工・管理業務をスムーズに進めることができます。
目次
非常灯設置基準に関わる建築基準法と消防法
非常用照明の設置基準を理解する上で、まず押さえておくべきなのが建築基準法と消防法の役割の違いです。この2つの法律は、それぞれ異なる目的で照明設備の設置を定めています。
建築基準法における非常用照明の位置づけ
建築基準法で定められているのは「非常用の照明装置」です。 これは、災害による停電時に、建物内にいる人々が安全に避難するための最低限の明るさ(視界)を確保することを目的としています。火災や地震で電源が断たれた暗闇の中、パニックに陥らずに廊下や階段を通って屋外へ避難できるようにするための設備です。
根拠となる条文は、建築基準法第35条および建築基準法施行令第126条の4、第126条の5です。この記事で解説する「非常灯の設置基準」は、主にこの建築基準法に基づいています。
消防法における非常電源と誘導灯の規定
一方、消防法では「非常用照明装置」そのものの設置基準は直接定めていません。消防法が規定しているのは、主に「誘導灯」と、スプリンクラーなどの消防用設備に電力を供給するための「非常電源」です。
誘導灯は、緑色の背景に人が走っているマークでおなじみの設備で、避難口や避難経路の方向を指し示す役割を持ちます。つまり、建築基準法の非常用照明が「明るさの確保」を目的とするのに対し、消防法の誘導灯は「避難方向の明示」を目的としています。
適用される法律の優先順位と関係性
「非常用照明」と「誘導灯」は、どちらか一方を設置すればよいというものではなく、それぞれの法律に基づいて両方の基準を満たす必要があります。
- 非常用照明装置: 建築基準法に基づき、避難経路の「明るさ」を確保するために設置。
- 誘導灯: 消防法に基づき、避難の「方向」を明示するために設置。
このように、2つの法律は異なる側面から建物の安全性を確保しており、相互に補完しあう関係にあります。建物の用途や規模によっては、両方の設置が義務付けられることを理解しておきましょう。
非常灯の設置義務が発生する建築物と場所
それでは、具体的にどのような建物に非常用照明の設置義務があるのでしょうか。建築基準法施行令第126条の4で定められている対象建築物と、設置が必要な場所について解説します。
設置義務の対象となる建築物の用途と規模
非常用照明の設置義務は、不特定多数の人が利用したり、避難が困難になったりする可能性のある、一定規模以上の特殊建築物などが対象となります。
| 対象となる建築物の種類 | 具体的な条件 - |
|---|---|
| 特殊建築物 | 劇場、映画館、病院、ホテル、共同住宅、学校、百貨店、工場、倉庫など、特定の用途に供する建築物。 - |
| 階数・面積による規定 | 階数が3以上で延べ面積が**500㎡**を超える建築物。 - |
| 大規模な建築物 | 延べ面積が**1,000㎡**を超える建築物。 - |
| 無窓の居室 | 採光に有効な窓などがない居室を有する建築物。 - |
(参考:建築基準法施行令 第百二十六条の四)
設置が必要な場所(居室・廊下・階段)
上記の設置義務がある建築物において、以下の場所に非常用照明を設置する必要があります。
- 居室: 特殊建築物の居室、階数が3以上で延べ面積500㎡超の建築物の居室など。
- 避難経路: 廊下、階段、その他、居室から地上に通じる避難の用に供する通路。
基本的には、停電時に人がいる可能性のある場所や、そこから地上へ避難するために通る経路全般に設置が必要だと考えてください。
【簡易診断】設置義務の有無チェックリスト
ご自身の関わる建物が該当するか、以下のリストで簡易的にチェックしてみましょう。
- □ 建物は劇場、病院、ホテル、店舗、共同住宅などの特殊建築物ですか?
- □ 建物の階数が3階以上で、延べ床面積が500㎡を超えていますか?
- □ 用途に関わらず、建物の延べ床面積が1,000㎡を超えていますか?
- □ 建物内に、採光のための窓がない、または有効な開口部がない「無窓の居室」がありますか?
これらのいずれか一つでも「はい」に当てはまる場合、非常用照明の設置義務が発生する可能性が非常に高いです。正確な判断には、緩和規定なども含めた詳細な確認が必要です。
建築基準法が定める具体的な設置基準
設置義務がある場合、次に満たすべき具体的な技術基準を確認します。基準は「照度」「構造・点灯時間」「電源」「配線」の4つの観点から定められています。
照度基準(床面で水平面照度1ルクス/2ルクス)
停電時に非常用照明が点灯した際、室内の床面において、水平面照度が1ルクス以上であることが求められます。 ただし、蛍光灯やLEDなど、蓄電池を電源とする照明器具を使用する場合は、電圧降下などを考慮し、より厳しい2ルクス以上の照度が必要とされています。
この照度は、JIS(日本産業規格)の測定方法に基づいて確認されます。設計段階や施工後の検査で、この基準を満たしているかどうかが厳しくチェックされます。
構造・点灯時間(30分間以上)の要件
非常用照明は、火災などで停電が発生してから30分間以上、継続して点灯し続ける性能が求められます。これは、消防隊の活動が本格化するまでの間、避難に必要な明るさを確保するための時間です。
また、以下の構造要件も満たす必要があります。
- 自動切替え: 常用電源が切れた際に、自動的に予備電源(蓄電池や自家発電設備)に切り替わること。
- 堅牢性: 火災の熱や衝撃、湿気などによって容易に破損しない構造であること。
電源の種類(蓄電池内蔵型・電源別置型)
非常用照明の予備電源には、大きく分けて2つのタイプがあります。
- 蓄電池内蔵型 照明器具本体にバッテリーが内蔵されているタイプです。個々の器具で完結するため設計や施工が比較的容易で、多くの建物で採用されています。定期的なバッテリー交換が必要です。
- 電源別置型(自家発電設備・蓄電池設備) 建物に設置された自家発電設備や、専用の蓄電池設備から電力を供給するタイプです。大規模な施設で採用されることが多く、複数の照明を一括で制御できます。配線には後述する耐火・耐熱性能が求められます。
配線方法の規定(耐火・耐熱配線)
電源別置型の場合、電源から照明器具までの配線は、火災の熱に耐えられるものでなければなりません。 火災時に配線が焼損してしまっては、非常用照明が点灯しないからです。そのため、建築基準法では以下のいずれかの方法で配線することが定められています。
- 耐火配線: 配線を耐火構造の壁や床、天井内に埋設する方法。
- 耐熱配線: ケーブル自体が一定時間火災の熱に耐える性能を持つ「耐熱電線」を使用する方法。
どちらの方法を選択するかは、建物の構造や設計によって決まります。
非常用照明の設置が免除・緩和される条件
建築基準法では、一定の条件を満たす場合、非常用照明の設置義務が免除されたり、基準が緩和されたりする規定(建築基準法施行令第126条の5)があります。コストや設計の自由度に関わる重要なポイントです。
採光が十分な居室や避難階の屋外通路
以下の場所は、停電時でも一定の明るさが確保できる、または容易に避難できると判断され、設置が免除されます。
- 避難階または地上に通じる出入口のある階で、避難経路となる廊下や通路。
- 採光上有効な窓などがあり、外部の光によって床面で1ルクス以上の照度を確保できる居室。
小規模な建築物や特定の用途の部屋
以下の建物や部屋では、非常用照明の設置義務がありません。代わりに、後述する「常備灯(懐中電灯など)」の設置でよいとされています。
- 一戸建ての住宅
- 長屋または共同住宅の住戸
- 学校
- 病院の病室、下宿の寝室、寄宿舎の寝室
- その他これらに類する場所
これらの場所は、利用者が空間に慣れており、パニックに陥る可能性が低いと想定されているためです。
国土交通大臣が定める特殊な構造
上記のほかにも、国土交通大臣が個別に安全性を認定した特殊な構造の建築物については、設置が免除される場合があります。これは非常に専門的なケースであり、適用を検討する際は、指定確認検査機関や所管行政庁への確認が不可欠です。
非常灯と誘導灯の目的と設置基準の違い
現場でよく混同されがちな「非常灯(非常用照明装置)」と「誘導灯」。この2つは目的も法的根拠も全く異なります。違いを正しく理解し、適切に設置することが重要です。
目的の違い(最低限の照度確保と避難方向の明示)
- 非常灯(非常用照明装置) **目的は「照度の確保」**です。停電時に空間全体をぼんやりと照らし、人々が障害物にぶつかったり転んだりすることなく、安全に移動できる最低限の明るさを提供します。
- 誘導灯 **目的は「避難方向の明示」**です。緑色のシンボルで「ここが出口です」「避難はこちらの方向です」と、具体的な避難ルートを視覚的に示します。
法的根拠の違い(建築基準法と消防法)
これまで解説してきた通り、法的根拠が異なります。
- 非常灯(非常用照明装置): 建築基準法
- 誘導灯: 消防法
したがって、検査や点検も、非常灯は建築基準法に基づく特定建築物定期報告、誘導灯は消防法に基づく消防用設備等点検と、それぞれ別の制度で行われます。
設置場所・デザイン・電源の違い比較表
両者の違いを一覧表にまとめました。
| 比較項目 | 非常灯(非常用照明装置) | 誘導灯 |
|---|---|---|
| 目的 | 避難のための最低限の照度確保 | 避難口や避難方向の明示 |
| 根拠法 | 建築基準法 | 消防法 |
| デザイン | 天井や壁に設置される白色の照明器具 | 緑地に白色のシンボル(ピクトグラム)が描かれた標識 |
| 設置場所 | 居室、廊下、階段など避難経路全般 | 避難口の上部、廊下・階段の曲がり角など要所 |
| 点灯時間 | 原則30分以上 | 原則20分以上(大規模・高層ビルでは60分以上) |
【用途別】非常灯の設置基準の具体例
ここでは、代表的な建物の用途別に、非常灯を設置する際のポイントや注意点を解説します。
事務所・オフィスビルの設置ポイント
事務所やオフィスビルでは、普段は照明がついていて気づきにくい「無窓の居室」に注意が必要です。 例えば、窓のない会議室やサーバールーム、倉庫などが該当します。これらの部屋は、たとえ小規模であっても建築基準法上の「無窓の居室」と判断され、非常用照明の設置が義務付けられる場合があります。
工場・倉庫の設置ポイント
工場や倉庫は、天井が高く、空間が広いため、規定の照度(床面で1ルクス以上)を確保するための照明計画が重要になります。 また、可燃性のガスや粉塵が発生する可能性があるエリアでは、引火を防ぐための防爆仕様の非常用照明器具を選定する必要があります。フォークリフトなどの往来がある場所では、接触による破損を防ぐため、設置位置や保護ガードの有無も検討しましょう。
店舗・商業施設の設置ポイント
不特定多数の人が利用する店舗や商業施設では、避難経路の分かりやすさが何よりも重要です。 内装デザインを重視するあまり、非常用照明が看板や装飾の陰に隠れてしまわないよう注意が必要です。特に、複雑な動線を持つ大規模店舗では、廊下、階段、通路の隅々まで、途切れることなく非常用照明を配置することが求められます。
共同住宅(マンション)の設置ポイント
共同住宅(マンション)では、各住戸内は設置免除となりますが、共用部分である廊下、階段、エントランスホールなどには設置義務があります。 特に、内廊下型のマンションでは、共用廊下が「無窓の居室」と同様の扱いとなり、非常用照明が必須です。定期的な点検やバッテリー交換は管理組合の重要な業務となります。

非常灯の設置基準に関するQ&A
最後に、非常用照明に関してよく寄せられる質問にお答えします。
LED非常灯への交換は法律上問題ないか?
全く問題ありません。むしろ推奨されます。 従来の蛍光灯タイプからLEDタイプの非常用照明に交換することは、消費電力の削減や長寿命化につながり、メンテナンスコストの面でも大きなメリットがあります。
ただし、交換する際は、建築基準法が定める性能基準(30分以上の点灯時間、規定の照度など)を満たしていることを示す認定マーク(例:日本照明工業会のJILマーク)が付いた製品を必ず使用してください。
定期的な点検と報告の義務について?
はい、点検と報告の義務があります。 非常用照明は、建築基準法第12条に基づく「特定建築物定期調査」の対象設備です。 一定規模以上の特殊建築物などの所有者・管理者は、専門の資格者(一級建築士、二級建築士または建築設備検査員など)に依頼して定期的に点検を行い、その結果を特定行政庁に報告する義務があります。いざという時に確実に作動するよう、適切な維持管理が求められます。
常備灯(懐中電灯)は非常灯の代わりになるか?
原則として、非常用照明装置の代わりにはなりません。 非常用照明は、停電時に自動で点灯し、空間全体を照らす設備です。一方、常備灯(懐中電灯)は手動で操作する必要があり、照らせる範囲も限定的です。
ただし、前述の緩和規定が適用される**「住宅の居室」や「学校」「病院の病室」など**では、非常用照明の設置が免除され、代わりにすぐに使える場所に常備灯を置いておくことで対応が認められています。
設置費用の相場や業者選びのポイントは?
非常用照明の設置費用は、「器具本体の価格」と「電気工事費」で構成されます。費用は器具の種類や設置台数、現場の状況によって大きく変動するため、一概には言えません。
業者を選ぶ際は、必ず複数の専門業者から見積もりを取り、比較検討することが重要です。また、非常用照明の設置は電気工事を伴うため、「電気工事士」の資格を持つ業者に依頼する必要があります。消防設備にも関連が深いことから、「消防設備士」の資格も併せ持つ業者であれば、より安心して任せることができるでしょう。
まとめ
今回は、非常用照明の設置基準について、建築基準法と消防法の違いから具体的な技術要件、緩和規定まで詳しく解説しました。
最後に、この記事の重要なポイントをまとめます。
- 非常用照明の目的と根拠法 建築基準法に基づき、停電時に避難するための最低限の明るさを確保することが目的です。
- 誘導灯との違い 消防法に基づく誘導灯は、避難の方向を明示するものであり、目的も法律も異なります。
- 設置義務の対象 一定規模以上の特殊建築物や大規模建築物、無窓の居室などに設置義務があります。
- 具体的な基準 床面で1ルクス(蓄電池電源では2ルクス)以上の照度を、30分間以上維持する必要があります。
- 緩和規定の存在 住宅の居室や学校、採光が十分な部屋など、設置が免除されるケースもあります。
非常用照明は、万が一の事態に人々の命を守るための重要な設備です。この記事で解説した内容を参考に、法令を遵守した適切な設計・施工・管理を行い、建物の安全性を確保してください。